土生玄碩(はぶげんせき)は江戸後期の眼科医で、宝暦12年(1762)、安芸吉田(現在・広島県安芸高田市)に生まれた。
 土生家は安芸郡山藩吉田で代々の眼科医として開業していた。広島浅野家の教姫の眼疾を治療したことを契機に、徳川幕府の御殿医に登用された。
土生家は安芸郡山藩吉田で代々の眼科医として開業していた。広島浅野家の教姫の眼疾を治療したことを契機に、徳川幕府の御殿医に登用された。
文政9年(1826)に、玄碩は江戸・長崎屋に逗留中の長崎・出島の蘭館医・シーボルトを訪ね、瞳孔を散大させる薬の情報と交換に、着ていた葵の御紋の入った紋服を差し出した。
シーボルトが持参していたのはベラドンナ(学名 Atropabelladonna L.)であり、シーボルトが教えた日本の植物は「ハシリドコロ」(走野老)であった。ヨーロッパ原産のベラドンナと日本のハシリドコロ〔原産:日本・ロウトウコン(莨トウ根)、学名Scopolia japonica Maxim.〕は、アトロピンやスコポラミンなどのアルカロイドを含み、瞳孔を散大させる作用があるので、使えば自内障の手術などに多大な威力を発揮した。
ところで、玄碩がシーボルトに与えた葵の紋服は、もとより将軍家拝領品である。後に、玄碩は、文政11年(1828)のシーボルト事件でこの件の責を問われ、晩年の大半を刑に服することになる。
すでに、幕府御殿医という地位・名声・富を得ていた玄碩が、敢えて国禁を犯してまで薬を入手しようとしたのは何故であろうか。常に新しい手術法を考案するために、あらゆることを貪欲に学ぼうという意欲に溢れる玄碩にとって、手術を容易にする散瞳剤を見逃すことができなかったのであろう。ひとえに、万人を救うことを最優先したと考えたい。それで題も「炎の眼科医」とした。
1440年頃土生玄碩の祖先渡辺義隆は、足利義教の家臣であったが、乱を避けて朝鮮に渡った。そこで7年間眼科学を修め、帰朝して安芸の上生(広島県府中市土生町)に住み、土生姓を名乗った。
1530年頃、土生玄碩から八代前の義賢が毛利元就に仕えて吉田に移り、眼科を業とした。
1600年頃土生玄碩の七代前の義道が毛利輝元に従って萩ヘ移った。義道の長男義次は萩から江戸へと移ったが、義道の次男義孝は吉田へ戻り、眼科を開業した。
玄碩は宝暦12年(1762)に生まれたが、誕生の正確な月日は不明である。名は義寿、字は九如といい、桑翁(そうおう)と号した。
当時、土生家の門柱には「めいしゃ 土生玄碩」と書かれていた。玄碩は趣味として三味線を習っていて、玄人の域に達していた。
あるとき、馬医者が、馬の眼の化膿症を三角鍼で角膜を切開して排膿する場面に立会い、 この眼を全快せしめた事例を経験した。
彼はこの経験から、人間の眼疾の化膿症に対しも、同様の排膿を試みて好成績を経験していた。ある両眼失明の患者が白内障に罹患したので、白い翳(かげ)を除こうと鍼を使ったが、失敗に終わった。
しかし虹彩の一部を切り、小さな孔が生じたために物が見えるようになっていた。すなわち土生玄碩は自分で穿瞳術を発明したのである。
玄碩はもともと大言壮語の輩であり、「ほら吹き目医者」と異名をとっていたが、この鍼を用いて目の化膿を排膿したり、自内障に穿瞳術を成功させて以来、その傾向が一層強くなっていった。
 あるとき三味線の師匠の家で稽古を受けていると、その師匠の盲目の友人が立ち寄り、自分は京都に居るときに、大坂(阪)の眼科医・三井元孺(げんじゅ)を紹介され、自内障を治療してもらい、見えるようになったと語った。
あるとき三味線の師匠の家で稽古を受けていると、その師匠の盲目の友人が立ち寄り、自分は京都に居るときに、大坂(阪)の眼科医・三井元孺(げんじゅ)を紹介され、自内障を治療してもらい、見えるようになったと語った。
このエピソードに、玄碩は三味線を習ったり、大言壮語である自分自身が恥ずかしくなり、そこで発奮して諸国を回って目医者としての修業を努めることを父・義辰の許可を貰い旅立った。
瀬戸内海沿いに備後、備中、備前と回ったが、当然当時の医療界の常識として、門外不出の秘密主義の家伝の治療法を、絶対他人には教示しない。
到々、京都まで来て、朝廷医官であつた和田東郭(わだとうかく・1744~1803)が開いていた漢方医学塾に入門した。
その塾で漢方医学と眼科学を学んでいたが、京都で行われた罪人の腑分け(解剖)に立会い、そのとき特別に頼んで眼球を貰った。そして眼を解剖したという。これが日本での眼科解剖の嚆矢であった。
彼が28歳のとき、京都から大坂に出て眼科を開業したが、全然患者が来ないために、鍼灸をして糊口を凌いていた。
そのとき按摩の修業をしていた“一止”と言う16歳の全盲の男の子が、「一度でよいからお天道さまを見てみたい」と土生玄碩に嘆いた。
土生玄碩は、実は自分が眼科医であり、白翳症(白内障)を治せる可能性があることを話した。そして一止の承諾を得て眼を手術し、幸いにも成功した。
このビッグ・ニュースは、たちまち大坂の町を駆け巡り、玄碩は「はやり」の「めいしゃ」になった。
和田東郭の塾で同門であった眼科医・高充国や前述の三井元孺らとも交流するようになっていった。高充国は、かつて蘭方医・杉田玄自の門下生であり、彼との交流によって土生玄碩は蘭方医学の進んだ知識に触れるようになっていた。
玄碩は30歳を越え、大坂での開業を止めて、故郷の安芸吉田に戻っていた。そしてさらに眼科医としての研鑽とともに蘭方医学も精を出して勉強していた。
享和3年(1803)、玄碩が42歳のときに、眼科医としての知識と技量が高く評価されたために、広島藩医に抜擢された。
文化5年(1808)4月、広島藩浅野重晟侯の第六女で南部利敬侯に嫁いでいた教姫が、江戸で重症の眼病に罹り、江戸に住む有名な眼科医たちが招かれた。しかし、眼科医たちの治療効果はなかったために、玄碩は広島からはるばる江戸の地まで招かれた。
幸い、玄碩の加療が効を奏し、教姫は全快された。そして土生玄碩の名声は不動のものとなり、江戸に留まって芝町に居を構えた。
文化6年(1809)6月23日、48歳になった玄碩は、第11代将軍徳川家斎侯に拝謁し、文化7年(1810)2月に奥医師を拝命した。
文化8年、彼は墓参のために安芸吉田に帰り、故郷に錦を飾った後、家族とともに江戸に移り住んだ。
さらに文化10年(1813)、法眼に叙され、文政5年(1822)に、第12代将軍徳川家慶の眼疾を治療した。
このように外様藩の医師が非常な速さで出世していったのは異例のことであった。
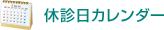
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
赤字の日が休診日となっております。